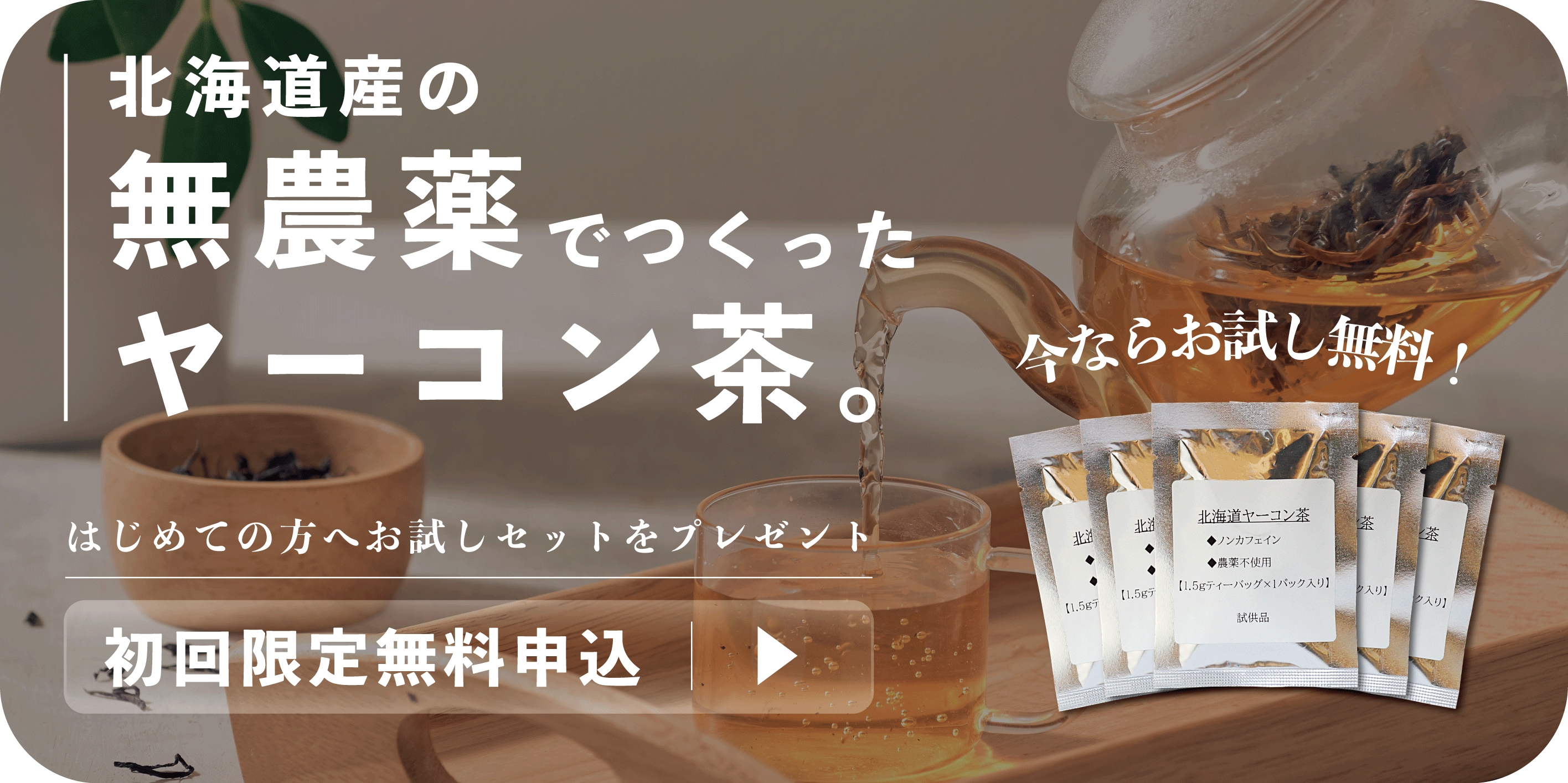ヤーコン茶は、食物繊維やポリフェノールを豊富に含むことから、腸内環境の改善や血糖値のサポートが期待される健康茶として人気があります。
hamayaでも、ヤーコン茶をご愛飲いただいているお客様が多数いらっしゃいますが、今回は「正しく理解して安心して飲むために」という視点で、ある医療論文を取り上げます。
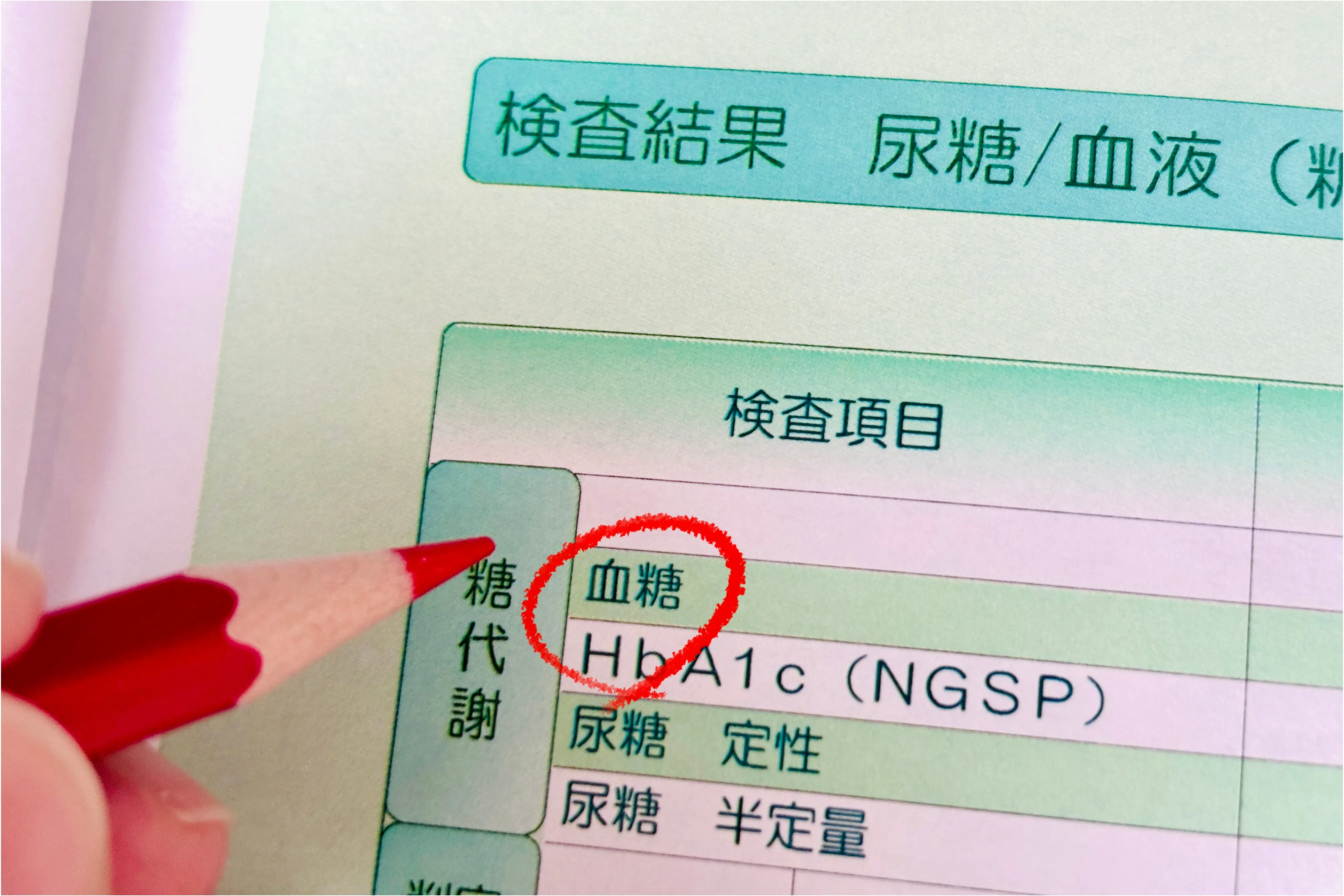
ヤーコン茶に関する症例報告とは?
2009年、日本消化器病学会雑誌に「ヤーコン茶摂取により肝機能障害を発症した可能性がある」という症例報告が発表されました。
- 論文タイトル:アルコール性肝硬変を背景に発症したヤーコン茶による薬物性肝障害の1例
- 著者:田中友隆 ほか
- 掲載誌:日本消化器病学会雑誌(第106巻 第6号)
- 論文リンク:J-STAGEで読む(PDF)
症例の内容と背景

この症例では、アルコール性肝硬変の既往がある66歳の女性が、ヤーコン茶を1日1〜2リットルのペースで飲み続けていたところ、肝機能の数値(AST・ALTなど)に異常が現れました。
医師による検査でウイルス性肝炎や自己免疫性疾患などは否定され、ヤーコン茶の摂取を中止したところ、肝機能は自然に回復。
この経過から、「ヤーコン茶が肝障害の一因となった可能性がある」と結論づけられました。
科学的な評価方法:RUCAMスコア

この症例では、世界保健機関(WHO)系のCIOMSによって提唱されている「薬物性肝障害診断スコア(RUCAM)」を用いて評価されており、因果関係のスコアは5点(可能性あり)とされています。
このスコアは、薬剤や食品などが肝障害を引き起こしたかどうかを科学的に評価するものです。
なぜヤーコン茶が影響を与えたのか?
ヤーコン茶に含まれる成分は、主に次の通りです。
- フラクトオリゴ糖(腸活成分)
- クロロゲン酸やカフェ酸(ポリフェノール類)
- その他植物特有の成分(未確認物質を含む可能性あり)
基本的には健康によい成分ばかりですが、「1日1〜2Lという多量摂取」と「既往の肝疾患」が重なったことで、肝臓への負担になったと考えられます。
「正しく、安心して」ヤーコン茶を楽しむために
hamayaでは、お客様に安心してヤーコン茶をご利用いただけるよう、次のような飲み方をおすすめしています。
● 初めての方へ
1日あたり200〜400ml(湯呑み2〜3杯分)からスタートし、体調に応じて調整してください。
● 持病や服薬がある方へ
医師へのご相談をおすすめします。特に肝臓疾患の既往がある方は、摂取を控えるか、専門家と相談しながらご使用ください。
● 継続のコツ
毎日ではなく数日おきにローテーションで取り入れるなど、“続けやすく、無理のないスタイル”が長く健康を保つ秘訣です。
健康食品と上手に付き合うために
今回紹介した症例はあくまで特殊な体調・背景を持つ一例であり、すべての方に当てはまるわけではありません。
しかし、健康茶やサプリメントなど、自然由来のものでも「合う・合わない」があります。hamayaでは、こうした正確な情報もお伝えしながら、お客様に安心して商品を選んでいただける環境づくりを大切にしています。
参考文献・出典
田中友隆ほか(2009)『アルコール性肝硬変を背景に発症したヤーコン茶による薬物性肝障害の1例』日本消化器病学会雑誌106巻6号
論文PDF(J-STAGE)
初回限定!ヤーコン茶を、まずは無料でお試ししませんか?
ここまでお読みいただきありがとうございます。
もしヤーコン茶にご興味をお持ちいただけたなら、まずは一度、その香ばしさとすっきりとした飲み心地を体験してみてください。

お申し込みは、以下の専用ページから簡単に行えます。
➡ ヤーコン茶・無料お試しパックの詳細・お申込みはこちら
ただいま【数量限定】で、ヤーコン茶 無料お試しパック(1.5g×5包入り)をプレゼント中です。
初めての方でも安心してお試しいただけるよう、送料もすべて弊社負担です。
※数量に限りがありますので、ご希望の方はお早めにどうぞ
▼お得なまとめ買いはこちらから

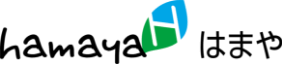

 悪質な偽サイト・詐欺サイトには
悪質な偽サイト・詐欺サイトには